「病院代が高すぎて払えない…!」そんなときに助けてくれるのが 「高額療養費制度」 です。
この制度のおかげで、 医療費が一定額を超えると払い戻しを受けられる のですが、 政府が「この制度の自己負担額を増やそう」としている ことをご存じですか?
もし変更されたら、 病院代が今よりも高くなる可能性がある のです。
ただ、今回 政府はこの負担増を「いったんストップ」することを決めました。
でも、これで安心…とはいきません。
今後、再び負担増が検討される可能性がある からです。
「高額療養費ってそもそも何?」 「どう変わる予定だったの?」 「なぜストップしたの?」
これらを わかりやすく、例を交えて解説 します!
そもそも「高額療養費制度」ってなに?
おそらく高額療養費制度について、理解している人の方が少ないと思います。
なので、なるべくわかりやすく説明をしたいと思います。
病院代が高くなりすぎたときの「ストッパー」
「医療費が高すぎて払えない!」そんなときのためにあるのが 高額療養費制度 です。
日本の健康保険では、自己負担は 通常3割 ですが、高額な医療費がかかると負担が大きすぎます。
そこで、 1か月に支払う医療費が一定額を超えると、超えた分が払い戻される 仕組みになっています。
例えば、手術で100万円かかっても…?
たとえば、会社員Aさん(40歳・月収30万円)が手術を受け、医療費100万円 がかかった場合…
- 通常の負担:100万円 × 30% = 30万円
- しかし、高額療養費制度を使うと 87,430円まで負担が軽減
- 約21万円が後から払い戻される!
このように 医療費の自己負担が一定額に抑えられる ので、大きな治療費が必要なときに助かる制度です。
簡単ではありますが、かなり国民としては重要な政策です。
なぜ今、この制度を変えようとしているの?
2025年に入ってから騒がれるようになった「税」問題がここで関係してくるのです。
詳しく簡単に説明していきます。
国の医療費が増えすぎてピンチ?

日本は 超高齢化社会 で、医療費がどんどん増えています。
日本人口1億2354万人で、内65歳以上の人口が3624万3千人で約3割です。
- 65歳以上の高齢者の医療費が 全体の約6割を占める
- これを 現役世代の健康保険料や税金で支えている
そのため高額療養費制度の負担がどんどん多くなってしまうため、今回自己負担額を引き上げるという政策を公表したみたいです。
法的文章に近いのでわかりにくいですが、簡単に説明すると高額療養費用の自己負担が上がってしまうということです。
今回の「自己負担引き上げ」とは?
Yahoo!ニュースの記事内容について、政府がどういった方針を挙げていたのかをまとめていきます。
高額療養費引き上げ“凍結” 自民党内から“突き上げ”も「選挙前にやらないで」(テレビ朝日系(ANN)) – Yahoo!ニュース
実際にどれくらい負担が増える予定だった?
政府は 2025年4月から高額療養費の自己負担限度額を引き上げる 予定でした。
この政策が実行されていた場合の上げ幅を表にしました。
高額療養費制度の自己負担限度額 引き上げ予定(凍結前の計画)
70歳未満
| 年収 | 現行(円) | 引き上げ後(円) | 増加率 |
|---|---|---|---|
| 約1,160万円以上 | 252,600 | 290,400 | 約15%増 |
| 約770万~1,160万円 | 167,400 | 188,400 | 約12.5%増 |
| 約370万~770万円 | 80,100 | 88,200 | 約10%増 |
| 約370万円以下 | 57,600 | 60,600 | 約5%増 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400 | 36,300 | 約2.7%増 |
70歳以上(外来)
| 区分 | 現行(円) | 引き上げ後(円) | 増加率 |
|---|---|---|---|
| 一般(1割負担) | 14,000 | 20,000 | 約43%増 |
| 一般(2割負担) | 18,000 | 28,000 | 約55%増 |
| 年間上限(1割負担) | 144,000 | 160,000 | 約11%増 |
| 年間上限(2割負担) | 144,000 | 224,000 | 約56%増 |
🔹 ポイント
- 70歳未満の現役世代 では 約5~15%の自己負担増 が予定されていた。
- 70歳以上(外来)の自己負担は大幅増(特に2割負担層は55%以上の増加)。
例えば、月収30万円の会社員の場合…
- 現在:1か月の自己負担限度額 87,430円
- 引き上げ後:100,000円以上に増加する可能性
つまり、 これまでよりも毎月1万円以上多く支払うケースが増える ということです。
この計画は凍結されましたが、将来的に政策決定される可能性は非常に高いです。
日本の高齢者増加が止まることがないので・・・
政府はなぜ「ストップ」したのか?

実は、政府は 「選挙前に負担増をすると国民が怒るから」「ただでさえ財務省問題があったのに、現行を通すことは無理」など多くの理由で、いったん引き上げを 凍結(延期) しました。
でも、これは 完全に中止されたわけではなく、将来的に再び議論される可能性が高い です。
もし引き上げが行われたら、どうなる?
将来的にこの政策が実行された場合、どんな影響があるのでしょうか?
あなたが病院に行ったときの負担はどうなる?
- 長期間の治療(がん、慢性疾患など)は負担が大きくなる
- 通院や入院の回数が多い人ほど影響を受ける
年収によって割合が変わってくるが、基本的に年収関係なく引き上げされてしまうので、通院している人や持病がある人からすると本当に困ったことになるでしょう。
8万が10万になって、2万増えるだけでも大きな影響になります。。。
どうしたらこの影響を減らせる?
小さな額かもしれませんが、手続きをすることで自己負担をする医療費を少なくすることもできます。
どうしても負担を減らしたい人のためにやった方がいいことを紹介します。
「限度額適用認定証」を知ってる?
「限度額適用認定証」 は、医療費が高額になったときに、病院窓口での支払いを一定額(自己負担限度額)に抑えられる証明書 です。
これだけではわかりにくいので、具体的に例を紹介します。
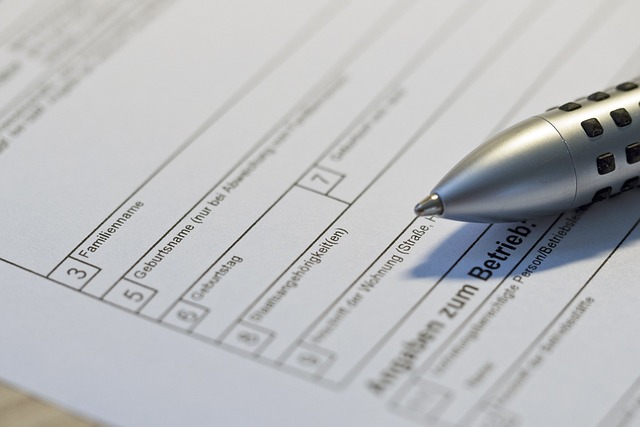
具体例:入院した場合の比較
イメージしやすいように具体的に例を出してみました。
ただし、年収や自分の状況によって金額が変わってくるので、しっかりと窓口に相談しましょう!
それでも申請が通れば、負担が少なく済むのでやるだけの価値はあります。
① 限度額適用認定証がない場合
- 手術+入院で100万円 かかったとします。
- 病院では 一旦100万円を全額支払う必要あり。
- その後、健康保険の高額療養費制度を利用して払い戻しを申請 する。
- 払い戻しには2〜3カ月かかる ので、しばらく大きな出費を抱えることに…。
② 限度額適用認定証を持っている場合
- 手術+入院で100万円 かかっても、窓口での支払いは自己負担限度額のみ。
- 例えば年収370万~770万円の人なら、約9万円の支払いだけ で済む(※自己負担限度額による)。
- 事前に申請するだけで、金銭的な負担がぐっと減る。
申請の流れ(簡単!)
- 自分の健康保険の窓口に申請(会社の健康保険組合、協会けんぽ、市役所など)。
- 申請書を提出(健康保険証やマイナンバーカードが必要な場合あり)。
- 約1~2週間で「限度額適用認定証」が発行 される。
- 病院の窓口で提示するだけ!
わからないことがあれば、住んでいる市町村のHPにアクセスして確認してみてください。
よくある質問(Q&A)
Q. どんなときに必要?
A. 入院や手術など、高額な医療費がかかるとき に申請すると便利!
Q. 申請しないとどうなる?
A. いったん全額支払わなければならず、払い戻しに 2〜3カ月かかる ことも。
Q. 外来でも使える?
A. 使えるけれど、入院のときほど効果は大きくない。(通院なら月ごとの合算で高額療養費制度が適用される)
ポイント
- 「限度額適用認定証」 があれば、病院窓口での支払いが 自己負担限度額だけ で済む。
- 高額な医療費(入院・手術など)の 立て替え負担がなくなる。
- 事前申請が必要なので、入院や手術が決まったらすぐに申請するのがベスト!
もしものときに備えて、手続き方法を確認しておくと安心!
医療費を抑えるためにできること

- ジェネリック医薬品(後発薬)を使う
- 種類にもよりますが、30%〜70%安くなります。
- 通院している人からすればかなり安く済むことになります。
- 不要な検査・通院を減らす
- 生活習慣をしっかりと見直して健康を意識すること。
- 予防医療を活用する(健康診断を受ける)
- 定期的に健康診断を行い、健康管理をしていく。
- 予防医療というものがあるので、そこの知識を取り入れ実行する!
国に対して私たちができることってある?
一番大事なことは、政治に関心を持つことです。
そして、選挙に行くことです。
これ以上・これ以下もありません。
今の仕組みを変えるなら、政治家を変えることが一番の近道です。
僕のこうの記事を読んで政治に少しでも関心を持ってくれると幸いです!
日本に住んでいる以上、人ごとでは無いですからね?
明日わ我が身って言葉があるように、急に環境が変わってしまうことはありえますからね・・・
まとめ
高額療養費制度は 病院代の負担を軽減する大事な仕組み ですが、 今後の制度変更によって負担が増える可能性がある ことも知っておく必要があります。
日本はこういったことが本当に多いです。
森林税がいつの間にか徴収されていることに気付いて無い人もいるでしょう。
「知らないうちに制度が変わってた!」 ではなく、 自分の生活にどんな影響があるのか、 しっかりチェックしておきましょう!

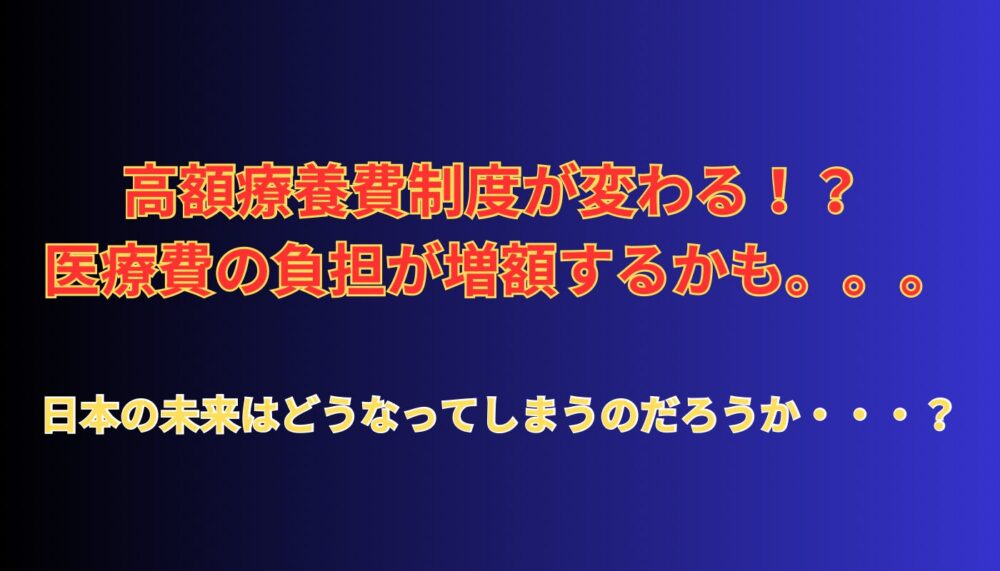
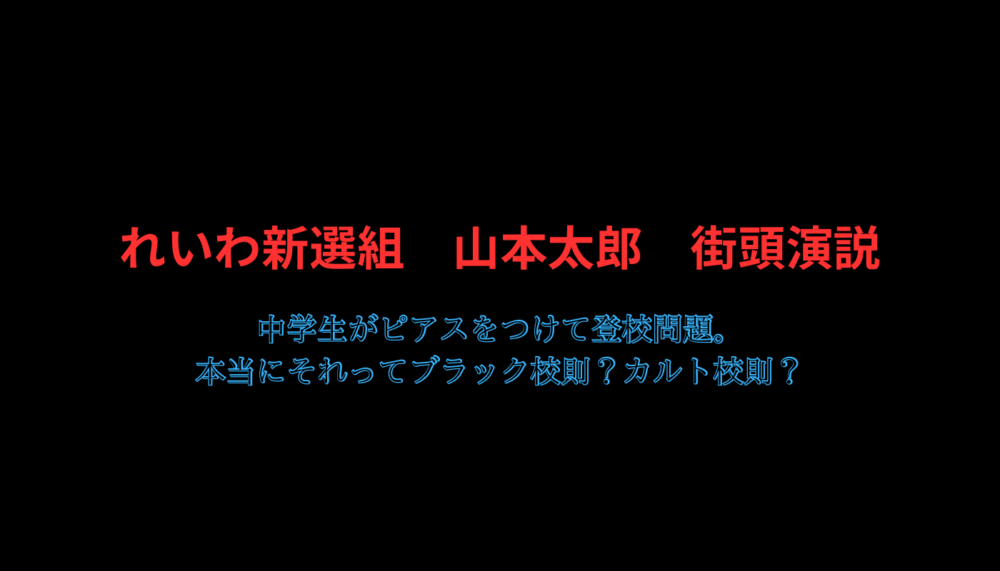
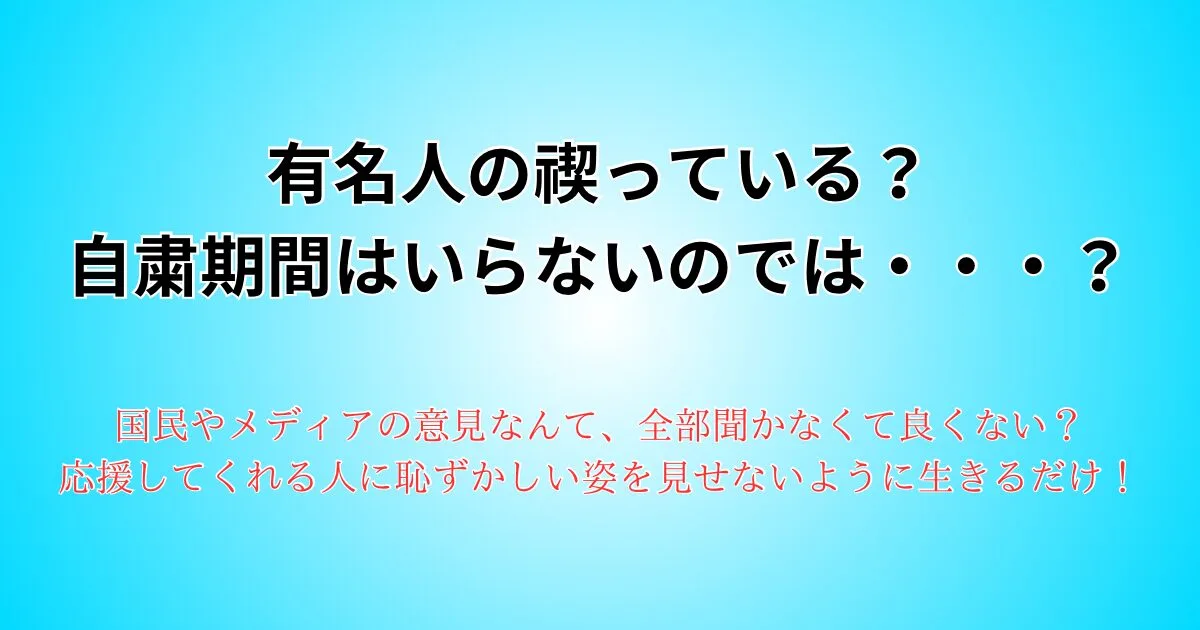
コメント