「結婚しても名前を変えたくない」そう思ったことはありませんか?
海外では当たり前のように認められている夫婦別姓。
しかし、日本ではなぜ制度としていまだ認められていないのでしょうか?
この記事では、法律・政治・社会の視点からその理由を分かりやすく解説し、読者が感じている疑問に寄り添いながら考察します。
第1章:そもそも夫婦別姓とは?
夫婦別姓とは、結婚しても夫婦がそれぞれの名字を保持する制度のことです。
おそらく多くの人は、
・苗字が違うだけなのにどうしてこんなに問題になっているの?
・法律でも、同じ苗字にしないといけない部分を変更するだけじゃん?
と思っている人が多いと思います。
現在の日本では民法第750条により、結婚する際に夫か妻のどちらかの姓を選び、夫婦が同じ名字を名乗ることが義務づけられています。
民法第750条とは・・・?
夫婦は、婚姻の際に定めるところにより、夫または妻の氏を称する。
選択的夫婦別姓とは、「別姓にしたい人は別姓を、同姓にしたい人は同姓を選べる」という制度です。
つまり、「別姓を強制する」のではなく、「選択の自由を保障する」仕組みです。
別姓にしたいと思う人はしてもらって構いませんよってことですね!
第2章:なぜ日本では制度として認められていないのか?
では、どうして日本では制度がないのか?
苗字を別にするだけのことでどうしてこんなにも苦戦をしているのでしょうか?
2-1. 法律と戸籍制度の問題
現在の民法では、夫婦は同じ名字を名乗らなければならないと規定されています。
これは日本の戸籍制度と深く結びついています。
日本の戸籍は「家族単位」で管理されており、同じ戸籍に入るには名字を揃える必要があるという考えが根強く残っています。
いわゆる○○家みたいなものがあったときの法律なので、どうしてもその固定概念が外れない感覚の人が多いという状態です。
おそらくここが一番の問題点だと思います!
戸籍で管理している部分もあるため、結婚していて苗字が別となるとたくさんの問題が連鎖してきてしまうことが問題になっております。
2-2. 政治的な対立と保守派の影響
ここの部分については、国民からすれば本当にどうでもいいことだと思います!!!
自民党を中心とした保守派の政治家や団体からは、「家族の一体感が壊れる」「伝統的な家族制度が崩れる」として反対の声が上がっています。
反対意見の弱さに愕然としますね・・・
家族の一体感って何ですか?伝統的な家族制度の崩壊?それが起こるとどういった問題が起こるのでしょうかね?
先ほど言ったみたいに国籍関係でトラブルが起こると言われた方がまだ納得できます。
こういったくだらない意見のぶつかり合いが起こるからまともな判断ができないのでは?って思いますね。
また、日本人独特の変化を嫌う習慣も大きく作用されているのも事実だと思います。
政治家がまともな議論をしていないのと同じように、国民もズレた議論をしているから進まないのだと思います。
2-3. 社会的な慣習・価値観
日本では「家族=同じ姓」という価値観が根強く残っており、姓が違うと家族として見られにくいという空気があります。※ツッコミどころ満載な発言ですがね。
特に年配層にその傾向が強く、親世代からの反発や心配の声も少なくありません。
また、「子どもの姓はどうするのか?」という疑問も多く見られます。
子どもの性はどうするのか?問題は本当に問題になってくると思います。
離婚をしていないにも関わらず、戸籍上どちらかの名前しか載っていないので、困ることになってくると思います。
特に子どもに対して問題が起こるでしょう。
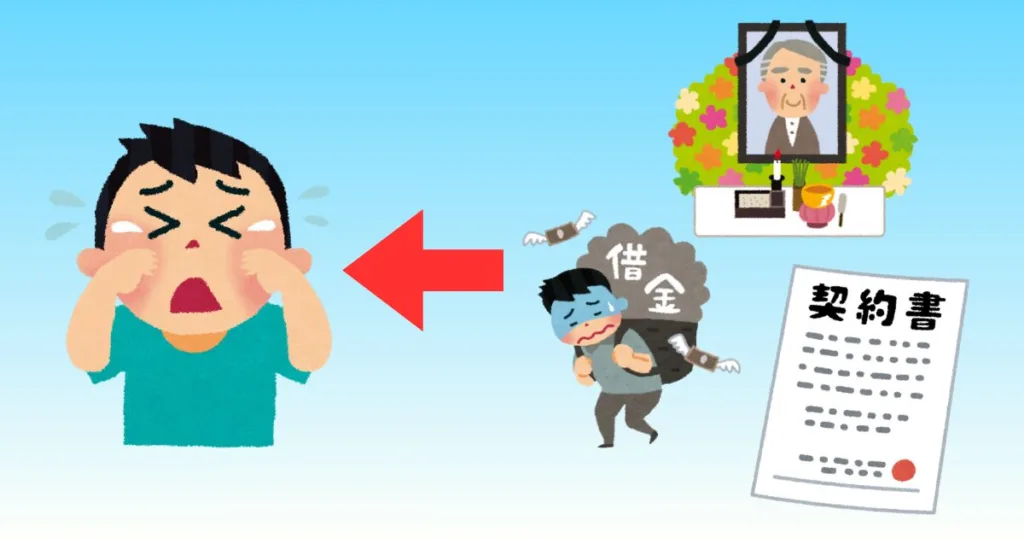
例えば・・・
選択的夫婦別姓をした夫婦がいるとします。
子どもは、父親の戸籍に入れたとしましょう。
その父親がクズで、借金をしまくって蒸発したとしたら、金融業者はどこに連絡をするかというと、戸籍に載っている子どもに連絡がいきます。
借金・父親死亡後の手続きなど関連したものを子どもがしりぬぐいをしなければならなくなります。
第3章:実際にはどんな問題が起きているの?
結婚をしてどちらかの苗字に変更することで、変更する側はどのような負担が起こるのかまとめました。
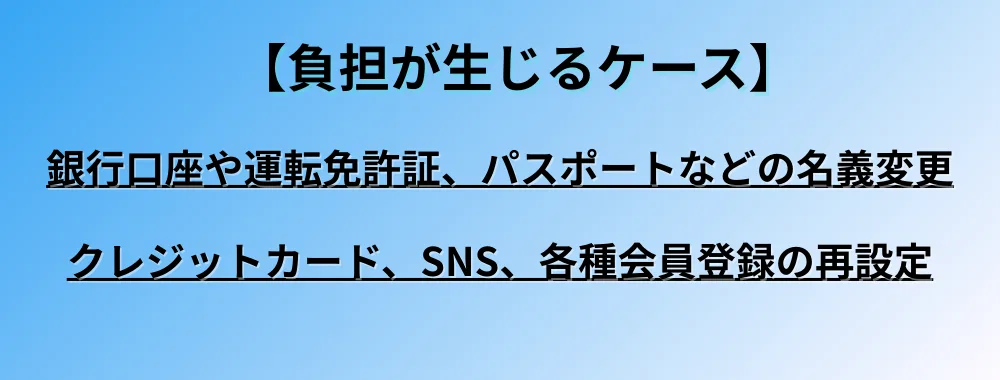
特に女性の側が、苗字を変更するケースが多いため、女性側の負担は大きくなってきます。
変更をするだけだと思っている人もいますが、働いている人からすれば平日に有給をとって関係各所に掛け合う必要があるので非常にストレスになってくることを理解しましょう。
こういった部分があるから、選択的夫婦別姓をしてほしいという声が上がってくるのです!
第4章:世界の国々と日本の比較
日本だけではなく、世界各国ではどういった動いになっているのかもみてみましょう。
アメリカ、カナダ、フランス、韓国、中国など多くの国では、夫婦別姓や選択的別姓が制度として認められています。
日本のように夫婦同姓が法律で義務付けられている国は極めて少なく、国連からも是正を求められた過去があります。
国際的には「選べることが当たり前」の時代に入りつつありますが、日本は今も「選べない」状況にあるのです。
第5章:私たちはどう考えるべきか?
選択的夫婦別姓は、「別姓を強制する制度」ではありません。
「同姓を選びたい人はそのまま同姓に」「別姓を望む人はそれを選べるようにする」ための制度です。
これにより、個人の価値観や生き方が尊重され、家族の形も多様化していくことが期待されます。
子どもの姓に関しても、工夫や制度整備次第で柔軟に対応できます。
すでに事実婚や旧姓使用で不便を感じている人が多い今こそ、「名前」に対する自由を考えるタイミングなのではないでしょうか。
まとめ
夫婦別姓が認められていない背景には、民法や戸籍制度といった法律上の問題、政治的対立、そして長年培われた社会的慣習があります。
こんなくだらないことを議論しているから、法律改正が進まないのだ。
増税関係に関しては、すぐに決まるくせに、自分たちが対応しなければならないような法案は全然進まない。
政治家の本来の仕事は、日本に住んでいる人に国民の声を反映させることが仕事では名のいのでしょうか?
相手の上げ足とっているような、低質な議論をしている暇があるなら行動してください。
国民が求めていることは、夫婦別姓にしたいということ。
それに伴っての問題回避策(子ども・名前に関する登録など)を考えて対応するだけ。
予算がどうのこうのは、夫婦別姓には関係ないですよ?
なら、さっさとできるできないの判断をしたらどうすか?
どこが、多様性の時代なんですか?
国会議員の数は、全部で700人越え。
一人くらいこれに対応してもおつりがくるとおもいますよ?
民間企業に勤めている営業担当でも、複数の顧客を相手にしているくらいですから、できますよね?
戻りますが、まずは、しっかりとできる・できないの結論を出したほうがいいと思いますよ。

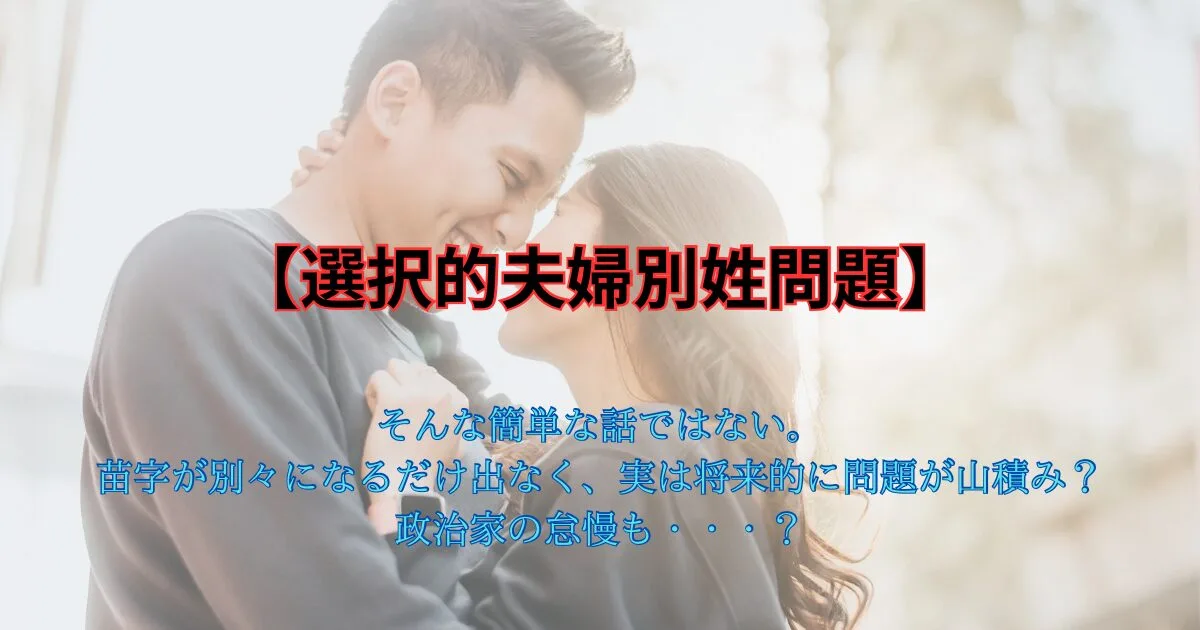
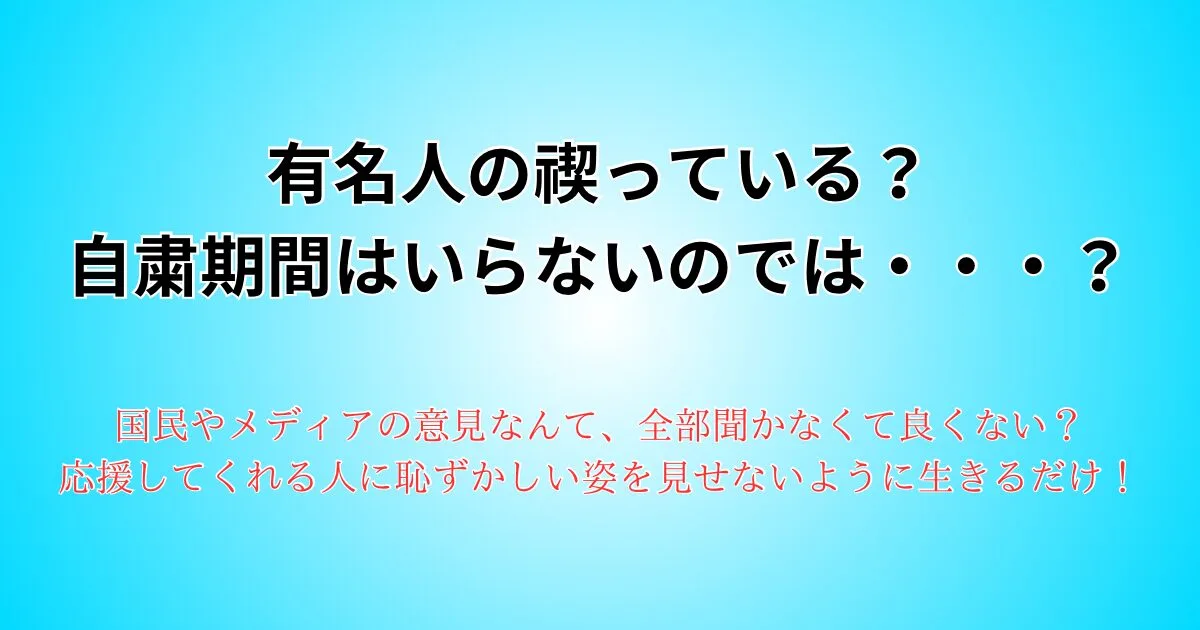
コメント